
育児も家事も仕事も、自分ひとりでこなす毎日がしんどい

限界かもしれない。離婚したほうがいいのかな
誰にも頼れず踏ん張っている方も多いのではないでしょうか。
ワンオペ育児は、体力だけでなく心までも消耗させていきます。そして、追い詰められた結果として“離婚”という選択肢が頭に浮かぶこともあるでしょう。
この記事では、ワンオペ育児が離婚につながる主な原因や、実際に離婚を進める際に知っておくべき制度・手続き、後悔しないための準備や考え方について解説します。
孤独な毎日から抜け出すヒントとして、少しでも心が軽くなるきっかけになれば幸いです。
ワンオペ育児とは?限界を感じてしまう理由
自分の心や体が壊れてしまいそうと感じたり、子どもにやさしく接することができなくなったりしていませんか?
育児がつらく、「もう頑張れないかも」と感じたとき、実はすでに限界を超えていることもあります。
ここでは、そもそもワンオペ育児とは何か、なぜそこまで追い詰められるのかを整理します。
「ワンオペ育児」とは周囲の支援なく子育てを担うこと
ワンオペ育児とは、パートナーや家族などからの協力が得られず、ひとりで子育てをこなしている状態を指します。
家事や仕事もすべて一人でまわす必要があることが多く、日々の生活に追われるなかで心身ともに疲弊してしまう人が少なくありません。
誰にも頼れない孤独感のなかで、精神的にも肉体的にも追い詰められてしまうのが実情です。
共働き・核家族の増加とサポート不足
共働き世帯が増える一方で、家事や育児の負担が母親に偏っている家庭は少なくありません。
さらに、核家族化の影響で近くに頼れる親族がいないケースも多く、育児を孤独にこなすことを余儀なくされている人が増えています。
社会全体としてサポート体制がまだ十分ではないこともあり、育児の負担が家庭内の一人に集中してしまう現状があります。
孤独感・ストレス・体調不良の実態
毎日子どもと過ごす時間のなかで、大人との会話がほとんどなく、孤独を感じやすくなります。
睡眠不足や過度なストレスによって、体調を崩してしまう人も多いです。
誰にも頼れない、話せないという状況が続くと、気持ちが不安定になり、自分でもコントロールできないほど感情が爆発してしまうこともあります。
子どもに当たってしまうことで自己嫌悪になり、さらに精神状態を悪化させていくこともあるでしょう。
ワンオペ育児が離婚につながる主な原因
ワンオペ育児が続くことで、夫婦関係にひずみが生まれ、最終的に離婚を選ばざるを得ない人もいます。
ここではよくある原因を大きく4つに分けて紹介していきます。
夫が子育てに非協力的・理解がない
育児は母親の仕事だと考えているパートナーに対し、不満を感じる人は多くいます。「手伝ってるつもり」の行動が、実際には負担の軽減になっていないケースも少なくありません。
たとえば、子どもが体調を崩したとき。
夜通し看病し、朝一番に病院の予約を取り、診察券やおむつ、着替えの準備まで済ませたうえで、夫には「病院へ連れていくだけ」を頼むという場面もあるでしょう。
ところが夫は、それ以外の段取りや片づけを見ておらず、「自分が連れていった」とだけ受け取ることもあります。
実際には、その間にママが吐き戻したシーツを洗い、部屋を除菌し、下の子の世話や食事の支度まで同時進行していることもあるのです。
こうした“見えない育児労働”が軽視され続けると、気づかぬうちに心がすり減っていきます。小さなストレスが積み重なり、夫婦の関係にひびが入ることもあるのです。
夫が仕事や趣味を優先し家にいないことが多い
仕事が忙しい、趣味の時間を優先してしまうといった理由で、夫が家庭にいない状態が続くと、妻の負担はますます大きくなります。たまには休みたいと思っているのは、妻も同じです。
それでも「仕事だから」「疲れているから」と言われてしまえば、誰にも頼れないまま自分ひとりで家事や育児をこなすしかなくなります。
子どもとの時間を共有せず、育児への当事者意識が乏しいと、パートナーへの信頼も失われやすくなります。
夫がいないあいだにすべてを回すことに慣れてしまい、「この人と暮らす意味ってなんだろう」と感じてしまう人も少なくありません。

ワンオペに慣れてしまうと、夫が帰ってくることでルーティーンが崩されることにいらだつこともあるんですよね…
夫婦喧嘩が増えて気持ちが離れる
育児や生活の価値観の違いから、日々の会話が衝突に変わってしまうこともあります。
話し合いができず、不満が積み重なると、怒りや悲しみだけが残るようになります。
「この人とはもう分かり合えない」と感じたとき、相手に期待しなくなり、離婚が現実味を帯びてくるのです。
子どもへの悪影響があると感じる
夫婦の不仲やストレスが子どもに伝わるのではと心配になることもあります。
親がイライラしていると、子どもも不安定になりやすく、家の中がピリピリとした雰囲気に包まれることもあるでしょう。
そんな環境が続くなら、いっそ別れたほうが子どもにとっても良いのでは、と考える人も少なくありません。

実際に私も喧嘩をしているときに、空気を読んで笑顔で話しかけてくる息子を見て胸が痛みました…
ワンオペ育児だけで離婚はできる?慰謝料や親権の現実
ワンオペ育児がつらくて離婚を考えても、実際に離婚できるのか、どのような準備が必要なのかを事前に知っておくことが大切です。
ここでは慰謝料や親権など、離婚に関する実情を見ていきましょう。
協議・調停・裁判の流れと必要な条件
まずはパートナーと話し合い、合意が得られれば「協議離婚」が可能です。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所を通じて「調停」や「裁判」へと進みます。
裁判になった場合は、法律上の離婚理由があるかどうかが問われます。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「ワンオペ育児だけ」では離婚が難しいケースも
ワンオペ育児がつらくても、パートナーが合意しない場合、それ自体が離婚の法的な理由にはならないこともあります。
裁判では、DVやモラハラ、長期的な別居などが立証されないと、離婚が認められない場合があります。
性格の不一致や不満だけでは、裁判で離婚が成立しにくい点に注意が必要です。
慰謝料や親権・養育費に関する注意点
慰謝料を請求するには、相手に不貞行為や暴力などの明確な落ち度が必要になります。
また、親権については、育児への関与度や生活環境の安定性などを考慮して決定されます。
養育費は法律で定められており、子どもの権利として請求できますが、支払いが滞るケースも少なくありません。
養育費に関する取り決めは、明確に行う必要があるでしょう。
離婚を後悔しないために考えておくべきこと
「離婚すればすべて解決」と思ってしまいがちですが、実際にはさまざまな後悔の声もあります。決断の前に、現実を見据えた準備が必要です。
離婚前に考えておくべきことをまとめました。
離婚後の経済的不安と生活設計
離婚後、経済的に苦しくなるのは避けられない現実です。
収入が減った状態で家計をまわすには、住まい、仕事、保育環境などの再構築が必要になります。

私は年度の途中から入れる保育所が見つからず、かなり苦戦しました…
制度の活用や、仕事探しなど、事前に生活設計を立てておくことで不安を軽減できます。

漠然とした不安に押しつぶされそうだったので、TODOリストを作ってひとつずつ確認していくと精神的にも少し楽になりました。
親権や面会交流の取り決め
子どもの親権や面会交流は、離婚後の親子関係に大きく影響します。
面会については具体的なルールを決めておくと、トラブルの防止につながります。
また、自身の気持ちを大切にしながらも冷静に子どもの利益もしっかりと考えることが大切です。

気持ちの整理がつかない状態で、役所の方に「子どもの権利だからあなたの感情は関係ない」と言われて大号泣しました。
ぜひ自身の納得する形を探してみてくださいね。
離婚を後悔する理由
離婚後に「こんなはずじゃなかった」と感じる人は少なくありません。
経済的な自立が想像以上に大変だったり、子どもを一人で育てる責任の重さに押しつぶされそうになったりすることもあります。
頼れる存在がいないなかで孤独を深め、話し相手も相談相手もいない日々に寂しさを感じるという声も多く聞かれます。
また、離婚によって物理的な距離が生まれたことで、元パートナーの存在がどれだけ育児や生活に影響を与えていたかに気づくこともあります。
時間が経つにつれて、自分自身が感情的になりすぎていたと振り返る人も少なくありません。

土日のショッピングモール、子連れの友人との会話など、離婚したことを実感するとやはり今でも気分が落ちてしまいます。
感情に任せて勢いで決めるのではなく、冷静に生活面・精神面・育児面すべての変化を見据え、離婚後の人生を見通してから判断することが後悔しないための第一歩です。
離婚を後悔した体験談
ワンオペ育児だけが理由ではないものの、離婚を経験した筆者が感じた「後悔」は主に2つです。
- 養育費の遅延
- 金銭面の清算不足
養育費については、取り決めはしていたものの支払いが遅れがちになり、毎月の生活費に不安を感じるようになりました。
特に子どもが成長していくにつれて出費も増えるなか、「この先ずっと、養育費が支払われるかどうかに不安を抱え続けるのか」と思うと、気が重くなります。
また、離婚時の金銭的な精算を曖昧にしてしまったことで、あとから困ることもありました。
たとえば夫婦時代に契約していたサブスクリプションや光熱費などの名義変更・解約手続きがうまく進まず、そのまま支払いが続いてしまうなどです。
精神的にも手続き的にも、非常に骨の折れる対応が必要となりました。
離婚そのものについては後悔していませんが、離婚を決めた時点で、もっと冷静にお金のことを整理しておけばよかったと強く感じています。
離婚前にできるワンオペ育児のつらさを軽くする方法
離婚を決断する前に、できる工夫や支援の活用で状況を変えられることもあります。
ここでは、離婚を回避するための対処法を紹介します。
夫婦で話し合いの場を持つ
毎日の育児や家事に追われるなかで、「もう話し合う気力もない」「何を言っても無駄」と感じてしまう人もいるかもしれません。
だからこそ、少しでも心に余裕があるタイミングを見つけて話す場を作ることが大切です。
まずは、感情的にならずにお互いの気持ちを伝えることを意識してみましょう。「責める」のではなく「伝える」スタンスだと、相手にも受け入れてもらいやすくなります。
「こうしてほしい」と具体的に伝えることで、相手に伝わる可能性が高まります。
もし難しい場合は、カウンセラーや第三者を交えて話し合うことで解決への糸口が見つかることもあるでしょう。
家事代行・育児支援サービスを活用する
すべてを自分一人でやらなくていいと気づくことが、負担軽減の第一歩です。
週に一度でもサポートが入ることで、心と体に余裕が生まれます。

サポートに来てくれた方が「どんどん頼って!いつでも来るからね」と言ってくださって、救われた経験があります。
自治体によっては民間よりも安くサポートが受けられたり、補助が出たりする場合もあるので、事前に情報収集をしておきましょう。
周囲の協力を得る・頼れる制度を知る
身近な人に話すだけでも、気持ちが軽くなることがあります。
地域の子育て支援センターやファミリーサポートなど、外部の制度を上手に活用することで、孤立感を和らげてくれることもあります。
助けを求めるのは甘えではなく、必要な力です。
離婚後に頼れる制度と支援まとめ
離婚後の生活を安定させるためには、利用できる支援制度を把握しておくことが重要です。
ひとり親になったときに「もっと早く知っていればよかった」と感じる制度は少なくありません。
申請しなければもらえないもの、条件を満たしていないと対象外になるものなど、ルールが複雑なケースもあります。
経済的な支えとなる制度を中心に、離婚後に使える公的支援を見ていきましょう。
児童扶養手当・ひとり親支援
ひとり親家庭を支える代表的な制度が「児童扶養手当」です。
離婚や死別などで父または母がいない家庭を対象に、子どもが18歳(一定の障がいがある場合は20歳)になるまでの間、月額で手当が支給されます。
- 支給額(令和6年度目安)
子ども1人:月額最大45,500円程度(所得に応じて段階的に減額)
2人目以降:加算あり(※正確な金額は年度や自治体により変動) - 申請に必要なもの
離婚証明書、戸籍謄本、所得証明、振込口座情報、マイナンバーなど
自治体によっては追加の書類が求められることもあります。 - 支給タイミング
原則として年3回(4月・8月・12月)に分けて振込
親と同居している場合、その親の所得も世帯収入として判断されるため、手当が減額または受給対象外になるケースもあります。実家に戻った後に「親の年金収入」で不支給になることもあるため、早めに役所へ相談することが重要です。

世帯分離していても私の住んでいる地域では支給対象外でした。
自治体によって内容・条件・申請時期が異なるため、「自分が何を使えるか」を確認するには、住んでいる市区町村の福祉課や子育て支援課に早めに問い合わせることが大切です。
年金・医療費・教育費の公的援助
ひとり親家庭を対象とした公的支援制度は、日々の生活を支えるだけでなく、将来への備えにもつながる重要なものです。
とくに年金、医療費、教育費の負担を少しでも軽減できる制度を知っておくことで、不安を減らし、必要なときにスムーズに支援を受けられるようになります。
- 国民年金の免除・猶予制度:収入が一定以下のひとり親家庭には、国民年金保険料の「全額免除」「一部免除」「納付猶予」といった制度があります。申請が必要ですが、老後の年金額を減らさないためにも追納制度の確認もおすすめです。
- 医療費助成制度(子ども・ひとり親):自治体によって異なりますが、子どもの医療費が無料、または1回数百円の負担になる制度があります。加えて、ひとり親家庭を対象に母(父)自身の医療費も助成対象となる地域もあります。
- 教育費の補助・就学援助:公立の小中学校に通う子どもを対象に、学用品費や給食費などを補助する「就学援助制度」があります。また、高校や大学の進学時には、奨学金や授業料の減免制度が設けられているケースも多くあります。
こうした制度は自治体によって対象や内容が異なるため、住んでいる市区町村の窓口で確認しておきましょう。
子どもの教育費についても、公立校を中心に補助制度が利用できるため、情報を整理しておきましょう。
シングルマザーの就労支援や奨学金
ひとり親が安定した生活を築いていくためには、収入の確保が非常に重要です。
シングルマザーを対象とした就労支援や、子どもの進学を助ける奨学金制度なども整備されています。
- マザーズハローワークの活用:子育て中の母親に特化した就労支援
保育所の情報提供や相談対応、子連れでの面接支援などが受けられます。求人の紹介だけでなく、働く環境づくりのアドバイスもしてくれるので、再就職の不安を軽減できます。 - 職業訓練・資格取得支援:国や自治体が実施する職業訓練制度
医療事務や介護職など、比較的就職しやすい分野のスキルを無料または低料金で学べます。訓練期間中に手当が支給されるケースもあり、収入が途切れる心配が軽減されます。 - 高等職業訓練促進給付金等事業:一定の資格取得を目指すシングルマザーに対して、最大月10万円程度の給付金(市区町村によって異なる)が支給される制度
資格取得後の就職につながるよう支援が受けられる点が大きなメリットです。 - 奨学金・就学支援:高校や大学の授業料免除、給付型奨学金、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金など、進学を諦めないための制度
所得によって利用条件は異なるため、進学先の学校や自治体での相談がおすすめです。

地域によっては、「オンラインマザーズハローワーク」で家にいながらサポートを受けられるようです!
「働きたいけどどう動けばいいかわからない」「子どもに進学をあきらめさせたくない」といった悩みを抱える人は、早めに情報収集して準備を進めておくと安心です。
離婚で後悔しないために相談すべき相手
離婚や育児に迷ったとき、すぐに答えが出せないのは当然です。
自分一人で判断を下そうとすると、視野が狭まり、精神的な負担が大きくなってしまいます。
だからこそ、信頼できる相手に話を聞いてもらうことが、冷静な判断につながる第一歩になることも。離婚を考えたときに相談してみてほしい相手を紹介します。
弁護士への無料相談
慰謝料や親権、養育費など、離婚に関わる法的な手続きについては、専門知識を持つ弁護士への相談が欠かせません。
多くの自治体や弁護士会では、初回無料相談を実施しているところもあります。
自分の状況を整理したうえで相談に行けば、法的にどのような選択肢があるのか、どのタイミングでどんな準備が必要かが明確になります。
調停や裁判に進む可能性がある場合でも、事前に情報を得ておくことで安心感が得られます。

私も法テラスで相談しました。無料相談の対象かどうか、相談の前に年収などが確認されます。
市区町村の相談窓口や支援団体
自治体の子育て支援課や福祉課では、ひとり親家庭向けの制度や手続きに関する相談に対応しています。
申請書類の書き方や制度の併用方法、緊急時の対応など、細かい部分までアドバイスが受けられます。
また、地域にはNPO法人やシングルマザー支援団体も存在し、母子生活支援施設や就労支援プログラム、無料相談窓口なども利用可能です。
役所とは違う視点でのアドバイスをもらえるため、併せて活用するのがおすすめです。
信頼できる友人・家族
身近な人に相談することは、心の安定にもつながります。
法的な助言はできなくても、感情を吐き出す場として重要な存在です。「何がつらいのか」「どうしたいのか」を話しているうちに、自分の考えや気持ちが整理されていくこともあります。
ただし、相手に負担をかけすぎないよう配慮しながら、安心して話せる相手を選ぶことが大切です。
「聞いてくれてありがとう」と伝えることで、関係もより良好になります。

離婚前後、友人に思いを話すことをしなかったため、私自身はしばらくふさぎこんでしまいました。今思えば信頼できる友人に話せばよかったと後悔しています。
まとめ|ワンオペ育児を理由に離婚して後悔する前に未来を考えよう
ワンオペ育児に限界を感じて離婚を考えるのは、決して珍しいことではありません。
ただ、「離婚すれば楽になる」と思っても、現実はすぐに変わらないこともあります。
焦って決める前に、今できることや支援制度を見直してみましょう。
そして、どんな選択をしても、自分や子どもが少しでも笑顔になれる未来を目指して、一歩ずつ前に進んでいけるよう備え、選択肢を持ちながら進んでいきましょう。

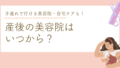
コメント